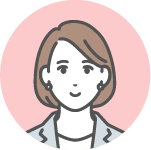※当記事は、ソニー生命から柴田1級ファイナンシャル・プランニング技能士へ執筆を依頼し、原稿をソニー生命にて編集したものです。
公的年金は課税対象となり、年金額が一定額以上になると税金が発生します。年金を受給している方やこれから受給する予定の方は、年金にかかる税金をどのように計算するのか気になる方も多いのではないでしょうか。
年金は老後生活を支える軸となる安定した収入ですが、最終的に手元に残るのは税引き後の手取り額です。そのため、安定した老後生活を送る上で、税金の計算方法を知っておくことは有意義です。
この記事では、年金にかかる税金の計算方法や税金がかからないケースなどを解説します。
年金にかかる税金はいくら?具体的な計算方法を解説!
公的年金の中でも、老齢年金を受給する際には受給額に応じて税金を納める必要があります。以下に該当する年金は所得税法における「雑所得」にあたり、課税対象となります※1
- 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
- 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
- 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、1.に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金
公的年金だけでなく、企業年金や共済年金なども課税対象となります。一定額以上の年金を受給すると源泉徴収される仕組みとなっており、税額の計算式は以下のとおりです。[注1]
(年金額-社会保険料控除・公的年金等控除などの各種所得控除)×5.105%
所得控除には、全員に適用される控除と個人の事情に合わせて適用される控除があります。年金受給者全員に適用される公的年金等控除後雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合、以下のように65歳未満の方と65歳以上の方で異なります。※2
【65歳未満の方】
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
| 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入金額-60万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5,000円 |
【65歳以上の方】
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入金額-110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5,000円 |
また、公的年金等控除以外にも以下のような控除があります。※3
| 控除の種類 | 対象者 | 月割控除額(1カ月あたり) |
| 公的年金等控除 基礎控除相当 |
全員 | 1カ月の年金支払額×25%+6万5,000円 (65歳未満は9万円が下限、65歳以上は13万5,000円が下限) |
| 配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる人 | その年の12月31日時点で70歳未満の配偶者:3万2,500円 70歳以上の配偶者:4万円 |
| 扶養控除 | その年の12月31日時点で16歳以上(特定扶養親族控除の対象者と老人扶養親族控除対象者を除く)の扶養親族がいる人 | 3万2,500円×人数 |
| 特定扶養親族控除 | その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人 | 5万2,500円×人数 |
| 老人扶養親族控除 | その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族がいる人 | 4万円×人数 |
| 普通障害者控除(*) | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害状態にある人 | 2万2,500円×人数 |
| 特別障害者控除(*) | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが重度の障害状態にある人 | 3万5,000円×人数 |
| 同居特別障害者控除 | 重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、扶養親族と同居している人 | 6万2,500円×人数 |
| 寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の人で、①または②に該当する人(夫の生死が明らかでない人も含む) ①夫と死別・離別後、婚姻していない人で子ども以外の扶養親族がいる人 ②夫と死別後、婚姻していない人で扶養親族がいない人 |
2万2,500円 |
| ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下の人で、子どもを扶養する単身の人 | 3万円 |
*普通障害者、特別障害者の定義については、日本年金機構「障害者とは」をご覧ください。
上記の表の中でも、配偶者控除以下の控除を「人的控除」と呼びます。人的控除を受けるためには、日本年金機構などから送られてくる「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
「扶養親族等申告書」を提出しないと、控除の適用となる条件を満たしていても控除を受けられません。その結果、必要以上に税金を支払うことになるため、注意しましょう。
例えば、65歳未満で年金収入が150万円、年間の社会保険料が15万円、扶養親族がおらず、他の所得控除もない場合は年間の所得税は1万1,000円(復興特別所得税を含めると1万1,200円)となります(*1)。65歳以上で年金収入が250万円、年間の社会保険料が30万円、扶養親族がおらず、他の所得控除もない場合は年間の所得税は3万1,000円(復興特別所得税を含めると31,600円)となります(*2)。
なお、公的年金の中でも障害年金と遺族年金は非課税です。また、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金や互助年金は公的年金には該当しません。
※1 参照:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
※2 参照:国税庁「高齢者と税(年金と税)」
※3 参照:公益財団法人 生命保険文化センターHP「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」
(*1)(年金額(1,500,000円)-社会保険料控除(150,000円)-公的年金等控除(650,000円)-基礎控除(480,000円))×5.105%≒11200円(100円未満切捨)
(*2)(年金額(2,500,000円)-社会保険料控除(300,000円)-公的年金控除(1,100,000円))×5.105%≒31,600円(100円未満切捨)
税金がかからないケース
公的年金を受給している方でも、収入が公的年金のみで以下に該当する場合は税金がかかりません。※3
- 65歳未満の方:年金受給額が108万円未満
- 65歳以上の方:年金受給額が158万円未満
上記の場合、所得税の基礎控除と公的年金等控除を合算すると課税所得がゼロになります。課税対象となる所得がないことから、所得税が発生しません。
なお、配偶者控除や扶養控除の適用を受けられる方の場合、控除額が増えます。その結果、受給できる手取り年金額も多くなります。
年金にかかる税金の各種控除制度
税額を計算する上で重要となるのが、年金額と控除額です。控除額が大きいほど、負担する税額を抑えられます。
以下で、年金にかかる税金の控除額や控除制度を解説します。
控除制度と年金
公的年金を受給している人に関連する控除は、先述した公的年金等控除のほかに雑損控除や医療費控除などがあります。※3 ※4 ※5
| 控除の名称 | 控除を受ける条件 | 控除される金額 |
| 雑損控除 | 災害や盗難等による損害を受けたとき | 次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額 (1)(損害金額ー保険金等の補てん金額)-(総所得金額等)×10% (2)((損害金額ー保険金等の補てん金額)のうち、災害関連支出金の金額)-5万円 |
| 医療費控除 | 納税者本人と生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費のうち、一定額を超えたとき | 次の式で計算した金額(最高で200万円) (実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)) (1)保険金などで補てんされる金額 (2)10万円 (注)その年の課税所得が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 |
| 寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄附をしたとき | 次の(1)または(2)のいずれか低い金額-2,000円 (1)その年に支出した特定寄附金の額の合計額 (2)その年の総所得金額等の40%相当額 |
| 社会保険料控除 | 納税者本人と生計をともにする配偶者や親族のために社会保険料を支払ったとき | 支払った社会保険料全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、企業型DC(確定拠出年金)及びiDeCo(個人型確定拠出年金)、心身障害者扶養共済の掛金を支払ったとき | 支払った掛金全額 |
控除額が大きくなるほど、負担する税額を抑えることが可能です。適用される控除がある場合は、忘れずに確定申告しましょう。
※4 参照:河内長野市「雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」
※5 参照:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
年金にかかる税金に関連したよくある質問
年金を受給している方やこれから受給予定という方は、確定申告が必要か疑問に感じていないでしょうか。
年金受給者に確定申告が必要かどうかは年金受給額やほかの所得の有無によるため、自分の状況をきちんと把握することが大切です。
年金を受け取ると確定申告は必要?
公的年金受給者の中で、以下に該当する方は確定申告が必要です。※3
- 2カ所以上から年金を受けている人
- 給与と年金を受けている人
- 年金以外にも所得がある人
- 医療費控除や生命保険料控除を受ける人
なお2.と3.に関しては、具体的には年金のほかに給与所得や配当所得などが年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。それぞれの所得において源泉徴収された税額を合算した「合計税額」と、実際に支払うべき「年税額」との過不足額を、確定申告で精算しなければなりません。
昨今は65歳以降も働く人が増えているため、確定申告が必要となる人も多いと見込まれます。確定申告を忘れてしまうと税務署から指摘を受ける可能性があります。
確定申告者数は上昇傾向にありますので、他人事とは思わずに注意しておきましょう。※6

なお、公的年金等の受給額が400万円以下で全部が源泉徴収の対象となっており、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
ただし、確定申告が不要な人であっても、確定申告をした方がよい場合があります。例えば、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「医療費控除」「雑損控除」などの適用を受けられる場合です。確定申告をすれば払いすぎた税金が還付されます。
※6 参照:国税庁「令和4年分の確定申告状況等について(まとめ)」
まとめ
公的年金を受給する際には、受給する金額や適用される控除によって所得税が発生します。受給者が最終的に使える金額は、税金や社会保険料が引かれた後の手取り額となる以上、公的年金にかかる税金の計算方法を把握することは欠かせません。
税金負担を軽減するための仕組みが、各種控除です。全員が受けられる基礎控除と公的年金等控除のほかにも、条件に該当するときに適用される人的控除があります。
本来であれば支払わなくても済む税金を支払わずに済ませるためにも、各種控除を確認し、扶養親族等申告書を忘れず提出することが大切です。年金を受給している方や年金受給を控えている方は、こちらの記事を参考にしながら負担する税金を計算してみてください。
SL24-7271-0325
ライフプランナーに
年金について相談する
執筆者:柴田 充輝(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
監修者:山口 貴弘(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
当資料は、2024年9月現在の税制・税率に基づき作成しておりますが、あくまでも概要について説明した参考情報(値)であり、その内容の正確性をお約束するものではありません。また、税制・税率は将来変更されることがあります。なお、個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署の判断によりますので、お客さまご自身にて所轄の税務署または税理士にご確認ください。