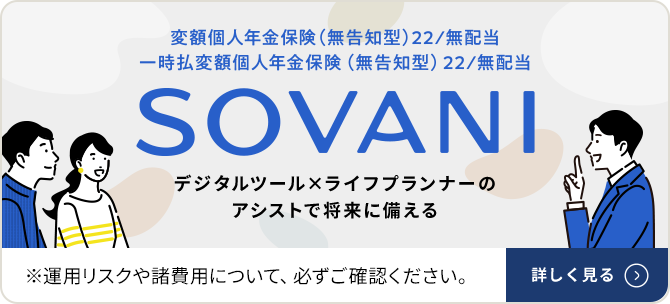資産形成とは?
資産形成に正式な定義があるわけではありませんが、個人が資産(財産)を形作ることを指します。将来の夢を実現し不安を軽減するために、資産がない状態から現預金や投資信託、株式、貯蓄型保険、不動産などを持つことで、徐々に資産を築いていくことを意味します。
働いて収入を得ることも資産形成の一環です。フロー(収入)の中から、一部を貯蓄や投資に回すことで、徐々に個人の資産を増やしていきます。資産形成をこれから始める初心者は、天引きや自動積立などで、自然に貯まる仕組みを設定し、継続していくのが、実は王道といえます。
「お金や資産に働いてもらう」という言い方もありますが、資産形成が進めば、ストック(資産)の運用も考えていくことになります。資産運用によって、資産からもお金が生み出される状態になっていけば、さらに資産形成が進んでいきます。
資産形成はなぜ重要か?
資産形成は、「将来の夢を実現し、不安を軽減するために行う」と前述しましたが、長い人生におけるさまざまなライフイベントでかかる費用をまかない、自分や家族の夢をかなえ、自分らしい人生を全うするためには、裏付けとなる資産が必要です。そのため、資産形成は非常に重要です。
結婚や住宅取得、子どもの教育、独立・起業をはじめ、お金が必要なライフイベントはさまざまなものがあります。たとえば、子どもが私立中高一貫校に通いたいと言い出したときや、大学時代に下宿生活をしたいと言い出したとき、よほど高収入であるか、祖父母などの支援があれば別ですが、資産がない状態では検討すらできないかもしれません。住宅取得においても、理想の家と出会っても、頭金がなくて住宅ローンの借りすぎになってしまうことから断念せざるを得ないケースもあります。資産形成は、人生の選択肢を広げるための方法ともいえます。
最も重要なのが老後資金です。資産形成をせずに借入などで乗り切っていくと、ツケは老後に回ります。退職金なども入り、一般的に保有資産がピークを迎える65歳時点で、資産から負債を引いた「純資産」がマイナスや0の状態では、老年期は年金だけで暮らすか、働き続けることになります。「人生100年時代」と言われる中、自分らしい老年期を送るには、資産形成は必須といえます。
もう一点、資産形成が重要である理由として、資産防衛の意味もあります。預貯金を中心に資産を保有していた場合、インフレが進むと、実質的な資産価値が減ってしまうリスクがあります。たとえば、年平均3%の物価上昇があったときは、利回り3%以上の運用ができないと、実質的に資産は減っていることになります。
資産形成の中に、株式や投資信託、不動産投資など、一定以上の利回りを狙える商品を組み込んで運用していくことは、資産価値を守る意味でも重要なのです。
老後に向けてどれくらいの資産が必要?
資産形成において特に重要となる老後資金について、必要額の考え方を整理しておきましょう。
平均的な生活に必要な資金
まず、老後に平均的な生活をするのに必要な資金がどれくらいか確認します。総務省「家計調査(年報)2022年」のデータによれば、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、支出(消費支出+税金・社会保険料等)が月26万8,508円となっています。一方、実収入が24万6,237円のため、月2万2,271円の不足です。65歳以上の単身無職世帯については、支出は15万5,495円で、実収入は13万4,915円。月2万580円の不足です。
これらのマイナス分を65~95歳までの30年分で累計してみると、次のようになります。
高齢夫婦世帯
2万2,271円×12カ月×30年=約802万円
高齢単身世帯
2万580円×12カ月×30年=約741万円
あくまでも全国の老後期の生活費から試算した平均データにすぎませんし、年金で暮らせるように生活を縮小できるなら、この差額分の貯蓄は不要です。
ただし、この試算はあくまでも生活費の部分だけです。車の買い替え資金、住宅のリフォーム・建て替え資金、介護資金、子や孫の結婚・住宅取得の援助資金をはじめ、生活費以外のライフイベントに伴うまとまった資金は含まないため、実際の老後資金としては、これにライフイベント費を上乗せして準備をする必要があります。
ゆとりある老後生活に必要な資金
生命保険文化センター「生活保障に関する調査(2022年度)」によると、夫婦2人でのゆとりある老後生活に必要な月額は、平均37万9,000円でした。
参照:生命保険文化センター「生活保障に関する調査(2022年度)」
希望額を聞いたアンケート調査の結果なので高めの金額になりがちですが、ここから前出の家計調査の高齢夫婦世帯の実収入24万6,237円との差額13万2,763円で試算すると、次のようになります。
ゆとりある生活費との差額(高齢夫婦世帯)
13万2,763円×12カ月×30年=約4,779万円
生活費の不足分を補う貯蓄だけで、約5,000万円必要という結果です。
資産形成における貯蓄と投資の違いとは?
さて、ここからは実際に資産形成を始めるための話です。将来に向けて資産形成をするには、「貯蓄」と「投資」の2つの方法があります。
貯蓄とは
貯蓄とは、お金を蓄えることをいい、一般的に金利は低いものの、元本割れのリスクがない元本保証商品での資産形成を指します。金融商品としては、普通預金や定期預金などが該当します。金利が低いことから「増やす」という面では期待できませんが、元本保証という安心感があります。
また、流動性が高く、日常の生活費など、すぐに必要となる資金は普通預金に預けることで、いつでも自由に引き出せます。金利が低くても元本割れがないのが貯蓄の特徴ですが、前述のとおり、インフレが進むと、実質的な資産価値が減ってしまうリスクがあります。
投資とは
投資とは、資産を効率的に増やすことを狙って、株式や債券、投資信託などの金融資産を購入したり、不動産や金といった現物資産を購入したりすることをいいます。貯蓄と比べて大きなリターンを狙える反面、投資にはリスクがあるため、元本保証がなく、投資した資金が目減りする可能性もあります。そのため、リスクを受け入れ、自己責任で行うのが投資です。預貯金と比べ、換金して引き出すまでに時間がかかり、流動性がやや低い点は知っておく必要があります。
一般的に投資に回せる資金は「3年以上使わない資金の3割以内」といわれるように、投資は短期で行うものではありません。5年、10年、場合によっては20年以上など、時間をかけて市場を育てていくような面があります。教育資金や老後資金など、中長期での資産形成に向きます。
資産形成の種類
具体的な資産形成に役立つ金融商品・実物資産について、貯蓄型と投資型に分けて整理しておきましょう。
貯蓄型商品
- 普通預金
- 普通預金は元本保証商品で、安全性は高いものの、金利が低く収益性は劣ります。しかし、流動性が高く、いつでも引き出せるのが特徴です。すぐに使う生活費や、何かあったときの生活予備費などをストックしておくのは、流動性が高い普通預金などが向きます。
- 定期預金
- 資産形成の第一歩として利用されることが多いのが、定期預金です。普通預金と同じく元本保証商品で安全性は高いものの、収益性が低めの商品です。一定期間預ける商品のため、普通預金よりは金利が高めです。定期預金は解約をすることで、期間中でも換金することができ、流動性も高いとされています。毎月、自動で積み立てる自動積立定期などでコツコツと貯蓄を進めるのに便利です。預入期間は1ヵ月から10年まであり、使用時期や金利を見ながら期間を選ぶといいでしょう。
投資型商品
- 債券
- 国や自治体、企業などが発行する有価証券で、発行体により国債、地方債、社債と呼ばれます。債券に投資をすることは、その発行体に「お金を貸し出す」ことを意味し、保有期間に所定の利子が支払われるほか、償還になれば額面通り戻ります。デフォルトリスクを評価した「格付け」を指標に投資しますが、格付けが高いほど金利は低くなる傾向があります。個人向け国債は1万円から購入できるなど、始めやすくなっています。
- 株式投資
- 上場企業の株式を買うことで配当金を得たり、売却益を狙ったりするのが株式投資です。企業によっては株主優待などを行うところもあります。大きなリターンが狙えて収益性は高いものの、企業の業績だけではなく、市場の状況などさまざまな要因で株価が変動します。投資元本を割り込むリスクもあり、安全性は低い投資です。また、換金するには、売却から3営業日かかることから、流動性も低めといえます。値上がりが期待できる企業を選ぶには、知識や経験などが必要です。
- 投資信託
- 投資家から集めた資金をファンドマネージャーが運用し、実績に応じて分配金が支払われます。また、基準価額が上がれば、売却益も狙えます。しかし、元本を割り込むリスクはあります。投資対象は、国内外の株式や債券、不動産などと幅広く、数千本の投資信託があります。日本株だけで運用する投資信託であっても、多くの株式に投資されるため、1銘柄だけに投資する株式投資に比べ、リスクが軽減されています。その代わり、リターンも下がります。運用は専門家にお任せのため、投資初心者でも始めやすい資産形成の方法です。なお、保有期間中は、信託報酬として運用コストが差し引かれます。
- FX(外国為替証拠金取引)
- FX(Foreign Exchange)は、為替通貨の売買で利益を狙う投資です。「外国為替証拠金取引」は証拠金を預けることで「外国為替」の取引を行えるのが特徴です。値上がりだけでなく値下がり局面でも、利益を得ることができます。レバレッジをかければ、少額で大きな金額の取引も可能ですが、投資元金以上の損失を被るリスクもあります。高レバレッジでの取引は、ハイリスク・ハイリターンの投資といえます。取り扱っているFX会社は金融庁の登録業者です。
- 不動産投資
- ワンルームマンションやアパートなどの不動産を保有し、家賃収入や売却益を狙う不動産投資も資産形成の1つとして挙げられます。相続などでもともと保有していた土地を有効活用して貸し出すケースも少なくありません。長期の資産形成に向き、実物資産のためインフレに強い投資ですが、換金して資金を取り出すには時間がかかり流動性はかなり低いのが特徴です。メンテナンスのコストはかかりますが、定期的に家賃収入を得られるだけでなく、売却益も収益となります。
- NISA
- NISA(少額投資非課税制度)は投資における税金の優遇制度で、売却益や配当金・分配金にかかる20.315%の税金が非課税で済みます。2024年1月からは、投資信託やETFの積立投資が可能な「つみたて投資枠」(年120万円まで)と、株式投資も可能な「成長投資枠」(年240万円まで)の両方を利用できるようになりました。非課税期間も無期限となりました。
- 資産を分散した金融商品である投資信託で、長期の積立投資を行うことは、リスクを抑えた投資の基本と言えます。「つみたて投資枠」で投資できる投資信託は、金融庁の基準をクリアした長期の積立投資に向く商品のみとなっています。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- iDeCoは任意で行う私的年金制度です。運用によって生じた収益が非課税であるだけでなく、掛け金が全額所得控除になり、また、60歳以降に一時金や年金として受け取るときも控除対象となるなど、さまざまな優遇税制が適用され、節税効果が大きい制度です。運用は、元本確保型商品(定期預金や保険)と投資信託から選んで行います。投資信託であれば、元本割れのリスクもあります。原則、60歳まで引き出せないので、老後資金以外の目的での運用には向きません。
- iDeCoについて気になる方は、こちらのページもご覧ください。
- ソニー生命の確定拠出年金(個人型)について
その他の商品
保障と貯蓄を兼ねた商品として、個人年金保険(定額型)や学資保険、養老保険などが挙げられます。保険料の一部が積立に回り、経過年数で解約返戻金が増えていく保険です。払込満了後に満期保険金や年金などが受け取れます。現在、これらの保険は加入時に決定する予定利率(運用利率。実際は、保険料算定時の割引率)が低めですが、予定利率が上がれば魅力が増します。
保険料の一部が運用に回る保険商品が変額個人年金保険です。運用の成果に応じて年金額も解約返戻金も増減する保険商品です。複数の特別勘定で運用され、契約者が運用の組み合わせなどを指示し、運用の結果にも責任を負います。元本保証はありません。平準払は、分散投資がなされた「特別勘定」で長期の積立投資を行うため、リスクを抑えた方法と言えます。
年代別の資産形成の方法は?
年代別に予想されるライフイベントを踏まえ、資産形成の方法を考えてみましょう。
20代の資産形成
20代は収入も少なく、資産形成に活用できる資金も少ない反面、今後のさまざまなライフイベントに備えていきたい年代です。そのため、まずは預貯金で生活費3カ月分の生活予備費を蓄えつつ、並行して、少額でつみたてられる資産形成を始めてはいかがでしょうか。投資体験を積むためにも、意味があります。
30代の資産形成
30代は子どもの教育や住宅取得などのライフイベントが想定されます。生活予備費は常にキープしながら、それぞれの目的や期間にあわせて資産形成を行いましょう。30代だと、貯めた資金をライフイベントで使った後の人もいるかもしれません。子どもの教育資金などは長期で準備していくため、子ども1人につき300万~500万円を目標に教育資金が必要な時期に現金化できるような資産形成を始めましょう。
40代の資産形成
40代は収入が安定する反面、子どもがいれば教育費負担が重くなる年代でもあります。また、自分の老後資金も考えないといけない年代でもあり、さらに、親が70代となり親のことで動く時間が増え始める年代です。
生活予備費はしっかりとキープし、子どもが中学校を卒業するまでに教育資金の目処を付けましょう。教育資金を終えた分で40代になったら老後のための資産形成を始めてみてはいかがでしょうか。親の介護問題については、資金的な余裕を作っておくことが大事になるので、いままで実施していた資産形成の積立額を増やしていくのも一法です。
50代の資産形成
50代前半は、一般的に収入が高いものの、55歳での役職定年などで収入減になるケースも。子どもが大学生で教育費がピークを迎えている可能性もあります。親のことでも40代に続いて時間が取られるほか、人によっては相続などが発生する年代。老後を考える際に、住宅ローンの残債が気になる人もいるのではないでしょうか。
生活予備費は生活費3カ月分をしっかりキープしつつ、老後資金準備のラストスパートとしてペースを上げて資産形成をするといいでしょう。住宅ローンの残債がまだある場合は、繰上返済を行うなど、働いている間に完済することがおすすめです。
資産形成におけるポイントやコツ
最後に、資産形成におけるリスクを軽減するためのポイントを整理しておきましょう。
ライフプランを立てる
前述で年代別の資産形成を考えましたが、あくまでも平均的な話です。同じ年代でも、ライフプランは人によって異なり、また家計の状況も異なります。自分自身のライフプランを立て、目的別貯蓄を実現していくことが大事です。
今後20年、30年の間にどのようなライフイベントがあるかを書き出し、そのためにどれくらい貯蓄すべきかを整理してみるだけでも、資産形成のモチベーションも上がり、具体的な資産形成プランを作成できることでしょう。
分散投資でリスクを軽減する
前述のように、資産形成方法にはいずれもリスクがあります。リスクを抑えるには、資産や地域を分散させて組み合わせる方法があります。前述のように、資産を預貯金だけで保有していると、インフレによって資産価値が下がってしまいます。一部を株式や投資信託、不動産などに分けて持つことがインフレリスクの軽減につながります。
分散投資には、「資産の分散」「地域の分散」のほかに「時間の分散」が挙げられます。まとめて一括投資をすると高値づかみのリスクがありますが、毎月コツコツと積立投資(定時定額投資)をすることで購入単価を平準化でき、リスクを軽減できます。
長期投資で複利効果を狙う
投資で得られた収益を元金に加えて運用することで、利子が利子を生む複利の効果があります。この複利の効果は投資期間が長いほど、大きくなっていきます。また、運用期間が長いほど、安定した収益が期待できるという傾向もあります。
資産形成を行う際には、短期決戦で成果を出そうとするのはリスクが高いので、長期スタンスでコツコツ積立投資をすることを考えるといいでしょう。複利運用の効果を活かすには、10年、20年など長期投資が基本です。
資産形成を始めましょう
資産形成は、まず始めることが大事です。何のためにいつまでにどれくらいの資産を持っていたいかを把握し、コツコツ積立をしていきましょう。投資系の商品だと、途中で上がり下がりはありますが、一喜一憂せず、10年、20年の長期のスタンスで、根気よく続けることが大事です。
これから資産形成を始めたい…
けど何から始めたらいいのか
わからないという方へ
保険・金融のプロフェッショナルソニー生命のライフプランナーが
あなたの資産形成を
営業時間 9:00~17:30 / 通話無料
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く
※「将来のお金を考えるブログ」はお金にまつわる幅広い情報をまとめています。当該記事コンテンツの中には、当社で取扱の無い商品・サービスを含んでいるものもございます。この点、充分ご留意のうえ、ご覧ください。
この記事の執筆者
-

- 豊田 眞弓
- FPラウンジ代表
AFP(アフィリエイティッド・ファイナンシャルプランナー)/子育て・教育資金アドバイザー
マネー誌・経営誌等のライターを経て、1994年より独立系FP(ファイナンシャルプランナー)。個人向けライフプラン相談や講師を務めるほか、コラム寄稿、書籍の執筆・監修などで活躍。亜細亜大学ほかで非常勤講師も務める。
 無料で相談する
無料で相談する